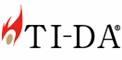今日、2025年1月17日で1995年の淡路島北部を震源とする巨大地震によって引き起こされた阪神淡路大震災の発生から30年を迎えます。当時、神戸市民だった事務局は上のテレビ画面を見ていません。
1年前にこのブログで震災直後の神戸の街の写真を掲載したので、もうここで震災について報告・紹介する必要はないかなと思っていました。
しかし、先日、たまたま出席した小中学校の同学年の同窓会が、30年前の1月17日午前5時46分を神戸港で一緒に迎えた同級生4人がそろう機会になりました。この4人が顔を合わせると、どうしてもあの朝、あの日の話になるのです。
事務局が神戸市民だった頃の友人のLINEグループでも、昨夜は30年前のあの日とそれからを振り返るメッセージが届き続けていました。30年めの1月17日を前に、みんな緊張していたのだと思います。


昨晩、神戸にいる友人から送られてきた東遊園地の写真を無断転載します。
「よりそう」の文字は17日の朝まで灯され続けていたそうです。
震災の街で歌われた「満月の夕べ」です。ソウルフラワーユニオンの曲ですが、今までにいろいろなアーティストによってカバーされています。上は二階堂和美さんのカバーです。やさしいうたごえとピアノの音色に心がゆさぶられます。
HEATWAVEの山口洋さんは、2016年4月24日にノエビアスタジアムでのVISSEL神戸とベガルタ仙台のゲームの前に「満月の夕べ」を演奏しています。被災地から被災地へのエールでした。
長田神社で行われたガガガSPのライブです。立ち上がる力を与えてくれるステキなアレンジです。
あの「満月の夕べ」から30年が経ち、今年の1月17日を境に阪神淡路大震災は「歴史」になるのではないかと感じています。
5年、10年、15年、20年、25年という節目を経て、今日の「震災から30年」はあっても、もう「震災から35年」「40年」はないのではないか、ということです。
今日の昼間に神戸市役所前で行われた「追悼と連帯、そして抗議のための集い」の案内です。今年が最後のとりくみとなります。本当は事務局も震災から30年の1月17日の朝を神戸の友人たちと過ごし、昼は市役所前にかけつけたかったのですが、目先の諸任務のためにそれはかないませんでした。
雇用や労働、住宅をはじめ震災後に被災地で表面化したさまざまな闘争課題も今は日常のたたかいに収れんされています。ひょっとしたら、もう震災そのものを語り合う機会はなくなるのかも知れません。なにせ、いまや神戸市民の半分があの震災を経験していないのだそうです。おそらく、神戸以外の阪神間の自治体でも同じでしょう。あの日とそれ以降の経験を忘れたいと思っている人も多いのかも知れません。
昨日、今日と天皇夫妻に被災地が蹂躙されてクソむかつきましたが、彼らはまさに震災の幕引きに来たのだろうと思います。
震災で犠牲になったのは「4600人」ではなく、6434人です。そして行方不明も3人います。
現職の兵庫県知事が震災の犠牲者数を覚えていなくても、震災はいろいろな形でこれからも人々の心と生活に影を落とし続けるはずです。
今日、公開になった「港に灯がともる」という映画の予告編です。
https://minatomo117.jp/
上が公式サイトです。震災を経験した世代と、経験していない世代のギャップも描かれています。事務局はこの映画に登場する新長田の丸五市場の焼きそば屋さんのおばちゃんに勧められて東京で行われた試写会に行きました。私の大学時代の先輩も製作に関わっています。多くの人に観に行ってほしいので、ここでは感想を書きません。
この映画にも関連しているのですが、震災直後の被災地では多くの労働者が解雇されました。地震そのものは天災ですが、その後の解雇や失業は人災です。雇用の確保と生活の再建が重要なたたかいの課題になり、地区労やユニオンの仲間たちが労働相談や解雇撤回のたたかいに取り組みました。そして、神戸地区労の仲間たちにより翌年5月から被災地メーデーが始められました。
以下は1996年5月1日に「ゆめたちあがれ」をスローガンに開催された第1回被災地メーデーのアピールです。
◎被災地メーデーアピール ゆめ たちあがれ
1886年5月1日。シカゴの労働者が8時間労働制を求めてゼネストに起ち上がりました。それは武装警官の発砲により多くの犠牲者が出る大惨事となりました。これがメーデーの歴史のはじまりです。働くものが人間らしい生活をするための当たり前の要求とたたかいがメーデーの起源です。
地震は30秒、しかしその「余震」はいまなお続いています。震災後1年余りを過ぎた神戸は、人口が10万人減ったまま。未だに「職」につけない人1万人。県外の工場へ強制配転された多くの人。店は再建したけれど、お客が戻らない商店街。仮設住宅での孤独死。転校先でイジメにあう子どもたち。小さな物音で目をさましおびえるお年寄り、幼児。もとの生活にもどれた人ともどれない人との溝は深くなり、あらたな差別さえ生まれています。
すべてを奪われたとき、最後に残ったのは「ひとのやさしさ」だと、私たちは教えられました。「僕は大丈夫だから」と瓦礫の下で最後まで家族を励まし続けて1人で逝った少年。1つのおにぎりをわけあった避難所生活。市外から救援物資を積んで駆けつけてくれた多くの人たち。全国から駆けつけてくれたボランティアたち。そんな優しさに囲まれて、生き残った私たちは今日まで頑張って来れました。
しかし、政府・行政は決してやさしくはありませんでした。復興対策の多くは山を越したと言います。住専処理に税金をつぎ込んでも、私たち1人1人の暮らしの復興には手を貸そうとはしません。基本的人権であるはずの「職」と「住」。それが保障されない国とはいったいなんでしょうか。被災地から本当の「日本」が見えます。
長田・神戸から全国へ、メッセージを送ります。元の生活を、そしていままで以上の生活を1日も早く作り出すため、私たちがもう1歩踏み出してみませんか。これまで無関心だったこと。他人まかせだったことに、もう少し目を向けてみませんか。たとえば環境。たとえば政治。たとえば市民運動。たとえば労働運動。1人の力は小さいけれど、みんなの1歩は必ず大きな流れとなります。その流れから、1人1人に優しい世の中をつくりたい。
ゆめ たちあがれ!被災地から。 1996年5月1日
この翌年、2回めの被災地メーデーのスローガンは「ゆめ ひろがれ」でした。10年が経った、2005年の「第10回被災地メーデー」のアピールも以下に紹介します。
◎震災10年 ふたたび若松公園へ
10年前の1月17日未明。私たちはこの日も普通の朝を迎えるはずだった。しかし、突然に神戸の街を大地震が襲い、激しく街を揺らし、人間を揺さぶった。家族を失い、家を失い、仕事を失ったおびただしい被災者は、なす術もなく、瓦礫の山と化した街を前に立ちつくすしかなかった。「豊かな国」のベールがはげ、実に貧しいこの国の姿があらわになった。
しかし、私たちはそこから歩き始めた。
わが国には、自然災害の被災者に対する公的援助の制度がなく、その考え方も存在しない現実。私たちは、震災被災者を先頭に、国の公的援助を求める運動を開始した。「法律や制度がないのであれば、それをつくってくれ!」――国会への請願行動、公的援助を求める署名活動が、神戸から全国に広がり、被災地の叫びは国会を動かす大きな力となり、『被災者生活再建支援法』が生まれた。この法律は、私たちが求めたものには遙かに及ばないものだが、その後の自然災害のたびに改善され、昨年の各地の台風災害、新潟中越地震の被災者にも適用された。
さらに、被災地の労働者を解雇の嵐が襲った。震災被害による事業所閉鎖や会社倒産に加え、便乗リストラが横行した。それはパート・アルバイトなどの非正規労働者に圧倒的に集中した、「人災」そのものだった。しかし、企業別に、正社員を中心につくられた労働組合の多くは、なす術を持たなかった。「被災労働者に労働組合がないなら、それをつくろう!」――兵庫県下、そして全国の働く仲間の支援を受け、全国初の「被災労働者ユニオン」が生まれた。便乗不当解雇を撤回させ、雇用保険の受給権を拡げ、失業者のライフ・ラインをつないで行った。この経験は、県下各地の労働組合の地域連帯運動、そして労働相談窓口としていまも引き継がれている。
震災翌年の1996年5月1日、私たちはこの若松公園で第1回被災地メーデーを開催し、今年で10回を数える。労働組合と地域住民が一緒に集い、大震災とその後の経験によって得られた"人間の連帯"を軸に、日本の社会の危険な流れに対して警鐘を鳴らし続けてきた。にもかかわらず、私たちは今回、身近なところで衝撃の大惨事を目にすることになってしまった。去る4月25日、JR福知山線で脱線転覆事故が起き、106人もの生命が奪われた。私たちは、深い悲しみとともに、「安全輸送」をかかげながら労働者には1秒を争う運転を強いていたもの、満員の乗客を乗せた電車をあの死のカーブに突っ込ませたものに対して限りない憤りを表明する。
私たちは、被災地メーデーの出発地であった、この若松公園に戻ってきた。
被災地神戸で、この10年間に私たちが紡いだ夢――「人間(ひと)は一人では弱いもの。しかし、人間(ひと)はつながり、それで生きることができる!」。
この夢は、私たち一人ひとりの胸に、いまも確かに宿っている。その夢をつなげよう。一緒に声をあげよう。新たな人災による犠牲者が生まれる前に! 2005年5月1日
被災地メーデーは2015年の「第20回」まで続けられました。上の写真は2004年の第9回被災地メーデーの様子です。神戸地区労加盟のたくさんの労働組合と一緒に、平和友好祭兵庫県実行委員会も出店していました。
昨夜の写真を送ってくれた友人から、あらためて今日の早朝の東遊園地の写真が送られてきました。
身動きできないほどたくさんの人たちがいたそうです。報道によると「つどい」には7万5千人が参加し、過去2番めに多かったとのこと。写真を送ってくれた友人の他にも友人、知人が何人か東遊園地にかけつけていたようで、後から報告が届きました。事務局もやっぱり神戸まで行っておけば良かったかも知れません。
5時46分は東京の自宅でテレビの前にいました。正座して画面を見つめていました。